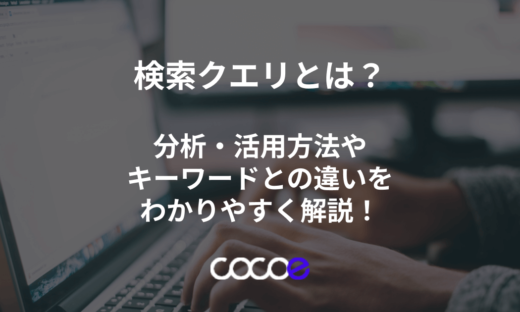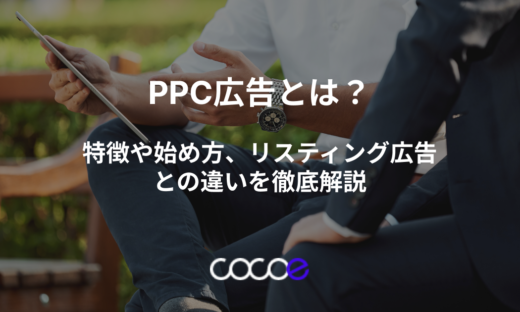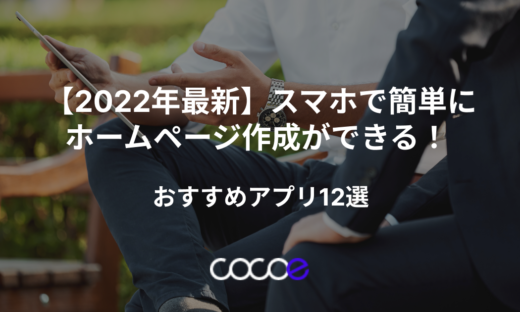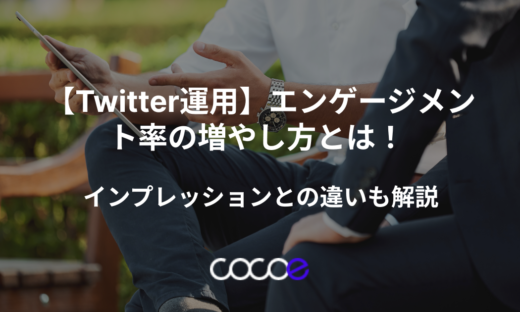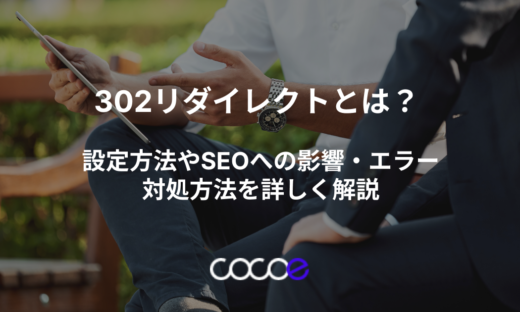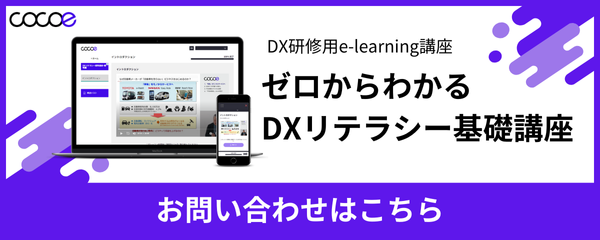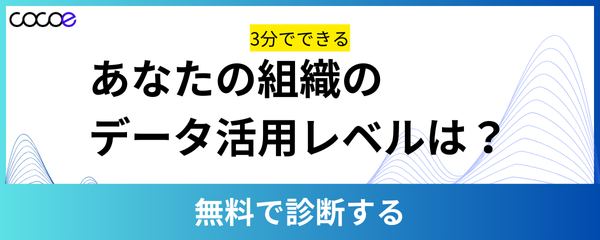今すぐできる!ホームページの検索順位を上げる10のコツとは?


▼目次
1.ホームページの検索順位とは?
2.ホームページの検索順位の仕組み
2-1.ホームページの検索順位が上がる期間について
3.ホームページの検索順位を上げるための対策
3-1.ドメインを正規化する
3-2.XMLサイトマップを作成する
3-3.パンくずリストを設置する
3-4.構造化マークアップを行う
3-5.表示速度を改善する
3-6.スマートフォン対応にする
3-7.タイトルや見出しにキーワードを盛り込む
3-8.質の高いコンテンツを作成する
3-9.良質な被リンクを獲得する
3-10.内部リンクを設置する
4.検索順位をチェックできるツール「Googleサーチコンソール」
5.まとめ
ホームページ運用担当者様が抱える悩みの多くは、ホームページの検索順位が上がらないことです。また、SEO(検索エンジン最適化)により検索順位を改善できることは知っているものの、難易度が高く二の足を踏んでいるケースもあります。
そこで本記事では、SEOにハードルを感じている方向けに、検索順位が決定される仕組みや、今すぐできる具体的な対策方法を紹介します。自社のホームページの課題を可視化し、実践に使える知識を身につけましょう。
1.ホームページの検索順位とは?
そもそも検索順位とは、GoogleやYahoo!などで検索したとき表示されるホームページの順番です。ユーザーの検索意図に合うコンテンツであると検索エンジンが評価するほど、検索順位は上昇します。
検索順位が上位表示されるとユーザーの目を引きやすく、URLのクリック率が高くなります。とある調査結果によれば、検索順位1位のクリック率は「13.94%」、2位は「7.52%」だそうです。つまり、その差は6%以上にもなり、6位以下になるとクリック率は1%を切ります。
ですから、多くの企業は自社ホームページを少しでも上位に表示させるため、SEOと呼ばれる「検索エンジンの最適化」を重視しています。
2.ホームページの検索順位の仕組み
では検索順位は、一体どのように決定されているのでしょうか。一見難しそうですが、実はたった2つのポイントを押さえれば理解しやすくなります。
1つ目は、クローラーと呼ばれるGoogleのソフトウェアがホームページ内を巡回し、情報収集している点です。そして情報がGoogleのデータベース内に保管(インデックス)されることで、検索結果として表示されます。
2つ目は、Googleの定めた判断基準(アルゴリズム)に基づいて質が高いと判断されたコンテンツに順位がつく点です。なお、Googleのアルゴリズムは200以上の項目があるとされますが、大まかな評価ポイントは4つに分類されます。
【検索順位の評価ポイント】
・コンテンツの内容
・ユーザビリティ
・セキュリティ
・被リンク
これら2つのポイントをまとめると、クローラーにインデックスされたうえで、Googleのアルゴリズムに従って優れたコンテンツを作成していけば検索順位が改善される可能性があります。
2-1.ホームページの検索順位が上がる期間について
SEOは中長期的な戦略が必要となる施策です。SEOは、対策を実施してから順位に反映されるまで、通常4カ月〜1年間かかるといわれています。これはGoogleも明言しており、近道はないと考えてください。
成果が出るまで時間がかかることを忘れないでください。変更に着手してからメリットが得られるようになるまで、通常は 4 か月から 1 年かかります。
引用元:SEO業者(代理店、コンサルタント)とは | Google検索セントラル | ドキュメント
SEOは一度対策を行なったら終わりというわけではありません。なぜならGoogleのアルゴリズムは年2〜4回更新されるからです。常にアンテナを張り、アップデートに合わせて最適化していくことが必要です。
>>>SEOについてはこちらの記事を参考にしてください
【初心者向け】SEOとは?マーケティングにおける重要性と基礎知識(テキストリンク)
3.ホームページの検索順位を上げるための対策

では早速、実践方法を紹介します。概要は以下の通りです。
【検索順位を上げる10のコツ】
- ドメインを正規化する
- XMLサイトマップを作成する
- パンくずリストを設置する
- 構造化マークアップを行う
- 表示速度を改善する
- スマートフォン対応にする
- タイトルや見出しにキーワードを盛り込む
- 質の高いコンテンツを作成する
- 良質な被リンクを獲得する
- 内部リンクを設置する
3-1.ドメインを正規化する
ドメインの正規化とは、同一または類似ページを1つに統一することです。コンテンツの重複は検索者の利便性を著しく低下させます。ですから、Googleはこのような事態を避けるため基準に反したコンテンツにはペナルティを与え、インデックスすらしなくなる可能性があるでしょう。
そこで、具体的な2つの対策を紹介します。
1つ目は、「301リダイレクト」する方法です。重複・類似するページURLの中で最も代表的なURLに評価を転送しさせることでペナルティの回避が可能です。
2つ目は、「canonicalタグ」を設置する方法です。HTMLファイルに専用のコードを記述することで、リダイレクトできない場合でもドメインの正規化が図れます。
3-2.XMLサイトマップを作成する
XMLサイトマップとは、クローラーにホームページ内構造を伝えるためのマップです。そしてXMLサイトマップをサーバー上にアップロードすることで、クローラーは早く、的確にホームページ内の構造を理解できるようになります。
XMLサイトマップはツールを使えば知識がなくても作成できます。
そこで、XMLサイトマップを簡単に作成できる便利なツールを2つ紹介します。
・sitemap.xmlEditor
ホームページのURLと設定を選ぶだけで簡単にXMLサイトマップを生成できる無料のツールです。
・XMLSitemapsGenerator
無料で500URLまで生成できる小規模ホームページ向けのツールです。
3-3.パンくずリストを設置する
パンくずリストとは、ユーザーがどのようなページ遷移で現在のページにいるのか視覚的に分かりやすくしたリンクのことです。一般的にはサイト上部に設置されていることが多く、「ホーム>コラム>SEO」といった形で表示されます。
ユーザビリティの観点からも取り入れたいパンくずリストですが、クローラーが巡回しやすいという点でも取り入れる必要があります。つまりXMLサイトマップと同様、クローラーがホームページ内構造を把握しやすくなります。
また、対策したい検索キーワードをパンくずリストに取り入れて設置すれば、上位表示されやすくなるというメリットもあります。
さらに、後述する内部リンク対策の効果もあるので、設置は必須といえるでしょう。
3-4.構造化マークアップを行う
レシピや求人情報を検索した時、検索結果に画像や動画が表示されているのを見たことはないでしょうか。これはリッチリザルトと呼ばれ、構造マークアップを行った結果、検索結果に表示されることがあります。
構造化マークアップとは、テキストや情報をタグ付けし、ホームページ内の情報を正しく伝えるための手法です。これによりクローラーはコンテンツ内容を理解しやすくなり、検索精度の向上につながります。
例えば、
・Q&A
・HOWTO
・動画
・商品
などのコンテンツは構造化マークアップが可能です。
また、構造化マークアップ無料作成ツール「SchemaMarkupGenerator」を活用すれば手間をかけず、簡単な操作で構造化マークアップを実現できます。
3-5.表示速度を改善する
表示速度とは、ホームページにアクセスした際、ページが表示されるまでの速さを測定したものです。表示速度が遅いページはユーザビリティが低いとしてGoogleに評価されないため検索順位に影響がでるとGoogleが公表しています。
検索ユーザーはできるだけ早く質問に対する答えを見つけたいと考えています。研究によると、ユーザーはページの読み込み速度を非常に気にかけています。読み込み速度はこれまでもランキング シグナルとして使用されていましたが、デスクトップ検索を対象としていました。そこで 2018 年 7 月より、ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素として使用することになりました。
引用元:Site Policies | Google Developers
主な対策内容は以下の通りです。
・画像の数、サイズの最適化
・HTMLなどのソースコード最適化
・ブラウザのキャッシュを利用する
・AMPを設定 ・高性能なサーバー利用
なお、ホームページの表示速度は「PageSpeedInsights(https://pagespeed.web.dev/ )」というGoogleが提供するツールで確認しましょう。URLを入力するだけで表示速度だけでなく、問題のある箇所や、どのように修正すべきか指摘してくれるので便利です。
3-6.スマートフォン対応にする
スマートフォンでも閲覧しやすいホームページ、いわゆるモバイルフレンドリーかどうかという点も検索順位で重要な判断指標です。パソコンの画面で見やすくても、スマートフォンでの閲覧が不便な場合、ユーザーにストレスを与えてしまうだけでなく、離脱率の上昇や、検索順位に悪影響を与えます。
例えば、Flashなどスマートフォン端末で利用できない技術は使わない、フォント・画像、ボタンサイズがスマートフォン画面でも最適化されているといった点で判断されます。また、自社のホームページがモバイルフレンドリーな設計になっているか、「モバイルフレンドリーテスト」というGoogleが提供するサイトでチェックできます。
もし、不合格だった場合、デバイスの幅に合わせて表示が最適化される「レスポンシブ対応」のデザインに変更しましょう。
3-7.タイトルや見出しにキーワードを盛り込む
上位を狙いたいキーワードがある場合は、必ずコンテンツのタイトルや見出しにキーワードを盛り込む必要があります。
下記のルールを守りつつタイトルや見出しを作りましょう。
・タイトルの文字数は30文字以内
・同じキーワードを複数回使わない
・キーワードはタイトルの左側に入れる
・具体的な数字を入れる・キーワードを羅列するのはNG
例えば、SEOの成功事例を紹介する記事の場合、下記のようなタイトルが考えられます。
OK例
SEOの成功事例5選!すぐマネできるテクニックを紹介
NG例
これさえすれば検索順位が上がる!成功事例から学ぶSEOで検索順位を上げる方法
OK例の方がシンプルで理解しやすいことがわかります。
3-8.質の高いコンテンツを作成する
良質なコンテンツの大前提は、検索者が求める情報が掲載されていて、コンテンツを読んで問題解決ができるかどうかです。ですから、多くの企業はキーワードを軸としたお役立ちブログやコラムを積極的に作成しています。
一方で、Googleからの評価が下がったり、最悪インデックスから外れたりする可能性があるため、絶対に作ってはいけないコンテンツもあります。ホームページ運用担当者様は以下のようなコンテンツ作りは避けなければなりません。
【インデックスが外される危険性あり】
・コピーコンテンツ
他のコンテンツをそのままコピーしてはいけません。
・隠しテキスト、隠しリンク
背景色と同化するようなテキストやリンクカラーにしてはいけません。
【評価が下がる可能性あり】
・検索者の意図にマッチしない
タイトルとコンテンツの内容が異なる場合、低評価を受けます。
・更新せずに放置
1度作ったきり更新がないホームページはどんどん評価が下がります。
コピーコンテンツや隠しテキスト化してしまっている場合、必ず改善しましょう。そのうえで、コンテンツ内容とタイトルの見直し、定期的な更新が不可欠です。
3-9.良質な被リンクを獲得する
外部サイトから数多くリンクされているホームページは、信頼性が高いと判断されます。しかし、リンクされていればよいというわけではなく、良質な被リンクでなければなりません。
そこで、どのような被リンクが効果的なのか解説します。
【良質な被リンク】
・関連性の高いホームページ
・月間PV数の多い著名なホームページ
・公的機関や病院など専門性・権威性があるホームページ
【悪質な被リンク】
・自作自演で設置したホームページ
・公序良俗に反したホームページ
・リンク集のみなど内容の乏しいホームページ
なお、Google Search Console(https://search.google.com/search-console/about?hl=ja )でどのようなホームページから被リンクされているか確認できます。そこまでナーバスになる必要はありませんが、定期的にチェックするとよいでしょう。
3-10.内部リンクを設置する
自社ホームページ内のページ同士をリンクさせることを内部リンクといいます。この内部リンクも、検索順位によい影響を与えるとされています。なぜなら、内部リンクを設置することで、ユーザーの利便性やクローラーの巡回性向上につながるためです。
ただし外部リンク同様、やみくもにリンクを張ればよいというわけではありません。重要なのは、リンク元とリンク先の関連性です。ユーザーは、コンテンツ内容の詳細や関連情報を求め、リンクをクリックする傾向にあります。ですから、ユーザーはコンテンツを閲覧して、次に何を知りたがるのだろうか?ということを熟考しましょう。
そうすることでユーザーはもちろんクローラーも巡回しやすいホームページとなり、結果的に高い評価につながりやすくなります。
4.検索順位をチェックできるツール「Googleサーチコンソール」
自社のホームページの検索順位を把握していますか?実は「Googleサーチコンソール」というツールを活用すれば簡単に確認できます。
Googleサーチコンソールとは、Googleが提供する検索分析ツールで、自社ホームページに関するさまざまな分析ができます。
【Googleサーチコンソールでできること】
・キーワードごとの検索順位を確認する
・特定のページの検索キーワードを確認する
・SEO的に問題のあるページを見つける
・表示速度を確認する
・被リンクを確認する
・モバイルフレンドリーか確認する
・XMLサイトマップを送信する
など
これらの優れた機能が無料で使えるので、自社ホームページのSEOに取り組む場合、必ず導入しましょう。
5.まとめ

Googleの検索順位決定基準や、その対策について紹介しました。1つ1つに焦点を当てると、意外に地道な作業がたくさんあると感じられたと思います。またGoogleのアルゴリズムは、定期的に更新されるため、昨日まで10位以内だったにもかかわらず、更新後30位にランクダウンする可能性もあり得ます。
ですから、SEO対策には専門知識が必要なうえに、常に更新・改善が必要です。そこまでできない方は、知識豊富な専門家に任せるのも1つの戦略です。
なお、株式会社ココエでは、SEO支援およびマーケティング分析をより深く学べる講座もご用意しております。
DX人材育成プログラム | https://www.cocoe.co.jp/dx-education
くわえて、サイト制作やDX支援などトータルサポートできる体勢が整っておりますので、気軽に問い合わせ、資料ダウンロードをお待ちしております。